|
Honda公式サイトの歴史ページはこちら T360 TN360~アクティ
ホンダの軽トラックが面白いのは、「うちはうち、よそはよそ」という独自の道を歩んでいるからではないでしょうか。
リアミッドジップエンジン、ド・ディオン式リヤサスペンション、荷台までフレームと一体になったモノコック構造、ビスカス式リアルタイム4WD、4WDでも副変速機やエクストラローギアを持たないシンプルな5速ミッション。高回転型エンジンとNA軽トラックで最もハイギヤードなギア比など、特徴だらけです。軽トラックが特別なものではなく、ごく普通の自動車であるということを目指しているようです。
T360(型式 前期型:AK250 後期型:BK250)
日本の量産車で、最初にDOHCを採用した車はなにかご存知でしょうか?  T360(写真提供:ホーネンスバカ研究員)

MAD-Rさんから、新規格アクティをT360レプリカ風に改造するキットが発売されています。 フルキャブオーバーに衣替えしたTNトラック TN360シリーズ(型式=車名)  オフ会の写真からですみません。右がTN360 Mタイプ。
T360は失敗作とされ、短命に終わりました。
代わって1967年に登場したフルキャブオーバー型のトラックがTN360です。前年にFF軽乗用車のN360が発売され、TNトラックはこのFFレイアウトをそっくり後輪に移植するというアイディアで生まれました。4気筒から2気筒のシンプルなエンジンになりましたが、馬力は同じ30馬力でした。 デフまで一体化されたFFのミッションユニットに、リーフリジッドのサスペンションを組み合わせるために、ド・ディオンという変わったサスペンション形式が採用されました。現在のアクティのスタイルはここで確立されたのです。 68には赤チェック柄の内装という派手な「Mタイプ」が追加され、69年には「デラックス」も登場しました。なお、マイナーチェンジごと車名が変わりましたが、2、4、6は存在しないようです。このページでのみ仮に(2)としておきます。 70年にはグリルが大型になり、車名も乗用車NIIIに合わせてTNIIIとなりました。そのバリエーションとして、オープン4シーターの「バモス」というユニークなモデルも発売されました。 71年には乗用車がNシリーズからライフになったのに伴って水冷エンジンが搭載されました。(それまでは空冷)(4)  グリルが大型化されたTN-III(トミカ)  バモス・ホンダ
72年には大幅なモデルチェンジ(ホンダではフルモデルチェンジということになっています)で前面デザイン一新、縦4灯の個性的なマスクのTN-Vとなりました。続いて73年には三角窓廃止と2系統ブレーキや助手席ヘッドレスト装備で安全装備を強化(仮6)。75年には排ガス規制に伴ってTN-7となりました。
 TN-V ナンバーは本来白だったはず。  
 TN-7 Vとの外見の違いは、ウインカー上のモールくらい。  TN-7 奥にあるのはアクティストリート この頃、他社では軽トラックをベースにワンボックスバンを発売しましたが、ホンダはTNトラックベースではなく、軽乗用車のライフをベースに72年に「ライフ・ステップバン」というFFのバンを発売していました。これは他社に比べればあまり売れなかったようですが、生産中止になってから人気が出てしまいました。さらに、ステップバンをトラックにした希少車FFトラック「ライフ・ピックアップ」もありました。
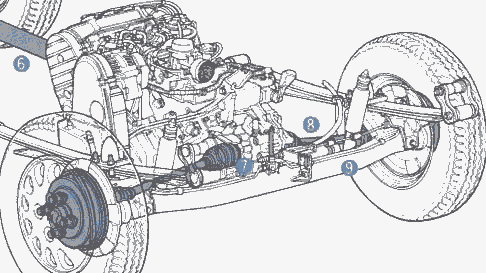
重量バランスに優れ、最低地上高とバネ下重量を稼げるのが特徴。
初期型:76年に軽自動車の規格が550ccとなったのを受けて、翌77年にTNトラックはフルモデルチェンジし、TNアクティとなりました。
基本構造は変わりませんが、1100ccのオートバイの4気筒エンジンを半分にしたというEH型2気筒550ccエンジンを搭載し、ボディも一回り大きくなりました。トラックの一部グレードにはサイドスカートが標準装備されています。 シリーズ通して2WD車のホイールは、10インチP.C.D120という特殊サイズです。インチアップする場合は古いシビック等のホイールを流用する必要があります。 また、79年にはアクティバンが、81年にワゴン風グレードの「アクティストリート」が追加されました。アクティバン/アクティストリートにはハイルーフも追加されましたが、この時点でのテールゲートは標準ルーフと同じ物でした。なお、このシリーズ通してリヤシートはフラット格納できません。 中期型:82年にはフロントパネルとインパネが大幅に変更され、近代的デザインとなりました。また、アクティストリートのみ当時流行の規格角型ヘッドライトとなりました。アクティバン/アクティストリートのハイルーフ車のテールゲートが専用設計となり、天井の高さまで開くようになりました。 同時にちょっとだけキャビンが広いトラックの「ビッグキャブ」、クラス初の5速マニュアルと「ホンダマチック」という変則オートマチックも追加されました。エアコンを追加すると足元にジュースを冷やせるクーラーボックスが付くなど、ホンダらしいユニークな装備もありました。 軽トラックに4WDが登場したのは80年からです。農家や雪国ではあっという間に4WDが主流となりました。 それに対し、ホンダは立ち遅れていました。FF用のミッションがベースだけに、前輪に行くギアーを追加するのが困難だったのです。結局、4WD化されなかったマツダポーターを除けばクラス最後発として、83年に4WDは発売されました。  TC 中期型(といっても4WDに初期型はありませんが) (ウインカーはクリアーレンズ風に加工してあります、本来は左ヘッドライト上にオレンジ色の「4WD」マークがありますが、剥がしてあります。) 2WDの中期型も外見上はステッカーとタイヤ以外はほぼ同じです。ストリートは規格角目で左右のガーニッシュの間にモールが付きます。 その4WDは、エンジンをミッションごと90度回転させ、縦置きとし、デフギアがあったところに4WDクラッチをとり付け、前後のデフを付け直すという大胆な手法でした。そのため、伝統のド・ディオンではなく普通のリジッドアクスルで、エンジン位置もかなり低い不恰好な下回りとなりました。荷台の高さのわりに、最低地上高が低かったのです。 当時は2WDの時の燃費を向上させるために前輪に「フリーハブ」という装置を組み込むメーカーが多かった中、ホンダはあえて採用せず、直進中ならいつでも4WDに入れられるというのをウリにしていました。 4WD+5速ミッション、前輪ディスクブレーキ、84年に発売された4WD+ATも当時唯一でした。ただ、そのミッション形式のため、副変速機やエクストラローはありませんでした。デフロックやリミテッドスリップデフもありません。 ホイールは4B-12インチ、P.C.D100、オフセット35で、2WD車と互換性はありません。 なお、この時点ではアクティバン4WD=標準ルーフ、アクティストリート4WD=ハイルーフという組み合わせでした。TNアクティビッグキャブの4WDは、シリーズ通して存在しません。  TC後期型(最終型)  VD後期型(最終型)ストリート いずれも4WDマークとタイヤ以外は2WDも4WDも同じ外見です。 後期型:更に85年にはフロントフェイスがマイナーチェンジし、アクティストリートが異型ヘッドライトとなりました。それに伴ってTNアクティ/アクティバンも台形ヘッドライトガーニッシュに変更されました。このガーニッシュは中期型と互換性があります。 TN-VからTNアクティ中期型まで「H-O-N-D-A」だったエンブレムが[H]マークに変更され、バンパーもそれまでの金属製からプラスチック製になりました。また、アクティバン4WDにハイルーフが追加されました。4WDステッカーがそれまでの派手なオレンジ色から地味なグレーに変わりました。 87年にはシートベルト規制に伴ってTNアクティ/アクティバンにも巻き取り式シートベルトが付きました(それまでは調節式。ただしアクティストリートのみ少し前から巻き取り式です)。この最終型はヘッドライトガーニッシュの内側がシルバー塗装されたのが見分ける方法です。 フルタイム化された 2代目アクティ アクティトラック(型式 550cc2WD:HA1 4WD:HA2 660cc2WD:HA3 4WD:HA4) アクティバン(550cc2WD:HH1 4WD:HH2) 660cc2WD:HH3 4WD:HH4) ストリート(型式はバンと同じ)  HA2 (これ以降の写真は、外見上は2WDも4WDもほとんど同じです)  左:550ccストリート(HH2)、右:550ccストリート改雪上車(HH1) 共に低グレード「L」ですが、右の顔がオリジナルで、左は管理人がカスタマイズしたものです。なお、この上のグレード「X」はサンルーフ装備、バンパーのみカラード(ガーニッシュは黒)でした。
550cc:ホンダの軽トラックはモデルライフが長いのが特徴です。他社が平均6~8年でフルモデルチェンジされるのに対し、TNトラックは10年、TNアクティは11年でした。
1988年にフルモデルチェンジされた2代目アクティも、実に11年という長い間販売されていました。 2代目アクティの最大の特徴は、ビスカス式のフルタイム4WDとなったことです。(商品名はリアルタイム4WD)これでホンダの全ラインナップからパートタイム4WDは姿を消しました。 当時実用車にフルタイム4WD!?と驚いたのですが、実際乗ってみると、足回を熟成しくく、タイヤの条件も厳しいバン・トラックだけに、フルタイム4WDの安定性が光りました。旧アクティを初め、当時の他の軽トラックとは別次元に感じました。 ミッションは4WDを前提として新設計され、4WD車もリアミッドシップレイアウトになりました。 また、トラックに「アタック」という低速ギア(ウルトラロー、ウルトラリバース)とデフロックの付いた農業仕様も登場しましたが、メインのギアはODのない4速で今ひとつでした。 2WDにはタコメーター付きの「SDX-II」(トラック、バン共)というグレードもありました。このSDX-IIとアタックのみスマートな形の角型パイプ鳥居と荷台作業灯が標準装備でした。 また、バンには前後2座席のタンデム乗り「PRO-T」、運転席と荷室が区切られた2人乗り「PRO-B」という営業仕様車が追加されました。 エンジンは3気筒1カム12バルブのE05Aで、550ccNA最高の34馬力、トルク4.5キロを誇りました。レッドゾーン7500回転まで実にスムーズな吹けあがりで、実にホンダらしいエンジンと言えるでしょう。ただし、タイミングベルトが細く、切れやすいという欠点がありました。 デザインは実にシンプルなもので、550時代のアクティは愛嬌のある丸目でした。管理人の個人的には、最初に見た時は「カッコワルイ」と思ったのですが、だんだん見なれてきて「カワイイ」と思うようになり、ドラマ「思い出に変わるまで」で財津和夫さんが丸目のバンに乗っているのを見て、「丸目が欲しい」と思うようになりました。 なお、ストリートは「アクティ」の名前が外され、デザインも全く別の異型ヘッドライトのものとなりました。ストリートには全車タコメーターが付いています。 また、HH系(新規格を含む)アクティバン、ストリート共に標準ルーフ車は存在しません。 ミッションは660cc後期型までシリーズを通して2WD車が4MT、5MT、3AT。4WD車が5MTと4+UL+URです。どこよりも早く採用されていた4WDのAT車は廃止されました。 内装では、ドアの内張りがプラスチック成型品となり、当時のホンダ車共通のインパネから続く曲線で囲まれた、風呂桶に浸かっているような感覚が特徴です。軽トラックとしてはかなり異質でした。 ミッドシップレイアウトを活かしてフロントシート下を空洞にし、トラックとバンの一部は助手席の座面を跳ね上げられるようにしてあります。トラックには不足しがちな小物入れ、バン/ストリートでは後席乗員がつま先を伸ばせるスペース、更にリヤピローを外さなくてもフラット格納できる機能まで備えました。なお、運転席下にはエアコンが納まります。 初代アクティには両席足元、ヘッドライトの裏にベンチレーター(導風口)がありましたが、2代目では運転席のみとなり、それも660ccの途中で廃止されています。 シリーズを通してトリップメーターはタコメーター付き車にのみ付いています。 翌年に装備変更のマイナーチェンジがあり、別売りで野暮ったいアングル鳥居しか付けられなかったSDXに、アタックと同じスマートな鳥居と荷台ランプが付くようになりました。 ただし、この鳥居は実質荷台長が1830mmと若干短く、業種によってはオプションのアングル鳥居の方が荷台が広く使えるという事情があったようで、鳥居なしも売られていました。 HH3初期型バン 660cc初期型:90年3月に軽自動車が660ccとなり、アクティはストリートと共通の異型角目の顔になりました。ただし、アクティはウインカーがオレンジレンズ、ストリートはクリアーレンズで差別化されています。なお、このクリアーレンズをアクティに移植する場合、レンズだけでは不十分(オレンジ球を入れれば法規的にはOKかもしれません)で、上はヘッドライトガーニッシュ、下はAssyで交換する必要があります。また、550cc車に移植する場合は下はちょっときついですがしっかり締めればOK、上(ストリートのみ)はガーニッシュに互換性がないのでレンズだけ交換し、オレンジ球を入れる必要があります。 グレード設定はほぼ同じですが、ストリートに中間グレードの「G」が追加されました。 エンジンは基本設計はそのままに、E07A型、38馬力5.5キロとなりました。このスペックは一時、日本の市販車中、最低のデータとなりました。スペック以上によく回るエンジンなのですが、E05A、E07Zと比べると微妙にがさつな感じがします。 翌91年8月にはマイナーチェンジし、排気ガス記号が「V」になりました。同時にSDXⅡに代わってタコメーター、ファブリックシート、ウレタンハンドル、カラードバンパー、AM/FMカセットステレオ、フルホイールキャップと装備充実した「タウン」が発売されました。SDX-IIが2WDだけだったのに対してタウンは4WDも設定されています。 なお、この時[H]マークの角が微妙に丸くなっています。  左:660cc初期型タウン(HA4)、右:550ccSDX(HA2) 共にオリジナルはウインカーレンズがオレンジです。 HA2はバンパーとヘッドライトガーニッシュを塗装しています。 HA4は純正フォグランプとサイドモールを追加しています。  HA4中期型 660cc中期型:まず93年10月にストリートがマイナーチェンジ。スモール/ウインカーがバンパーからヘッドライトと一体のような位置に移動しました。サンルーフ付きのモデルはインジェクションエンジン、パワーステアリングが追加されて「Xi」というグレード名になりました。また、5速+デフロックミッションを装備し、リヤシートが簡素化された「FOX」というグレードが追加されました。 遅れて94年1月に、アクティも同じ顔にモデルチェンジしました。こちらは顔以外の変更点は少ないのですが、運転席足元、ヘッドライト裏にあったベンチレーターが廃止されています。 なお、同年10月にはエアコンの触媒(ガス)が環境対応の新フロンガスに変わっています。ガスチャージの際はご注意ください。 このモデルはアクティ、ストリートともにウインカーレンズがオレンジ色です。 アタックをベースに後輪を2軸化し、クローラー(俗に言うキャタピラー)を装備した「アクティクローラー」が追加されています。クローラーに代えて通常のタイヤを付けることもでき、6輪車として走行することも可能だそうです。  後期型HA4 660cc後期型:96年1月、中規模マイナーチェンジです。熱線吸収グリーンガラス採用、アクティのラジオが電子化されて時計が付き、そのコネクターも4Pから6Pになりました。 アクティバンのSDX-IIが「SDX-Hi」というグレードになり、インジェクションエンジン、パワーステアリングが標準装備になりました。また、バンのSDXと2人乗りグレード「PRO-A」にもパワーステアリング、タコメーター、トリップメーターがオプションで装備できるようになりました。 ストリートはFOXが廃止、インジェクションエンジン、パワーステアリング付きのサンルーフなしグレード「V」が設定されました。 このモデルはオレンジだったライト下のウインカーが、クリアーレンズになっているのが特徴です。  中~後期型にはオプションで果樹農家用ミニ鳥居が発売されていました。これは一般的なコンテナが1段につき12個(普通の角パイプ鳥居は11個)積めるようになっています。ただし、荷台作業灯はなくなってしまいます。 (型式 トラック2WD:HA6 トラック4WD:HA7 バン2WD:HH5 バン4WD:HH6) はこちら。 
基本的に、TNアクティから現行型まで似た感じです。テール、サイドのキャラクターライン(補強のためのプレス)もほぼ一緒です。
直線基調ながら微妙に角を丸くしたようなデザインがアオリまで続いています。 テールライトはHA型以降共通で、バックランプが赤レンズの中に収まっていて、左右にあります。TNアクティも互換性はありませんが似た感じのデザインです。 テールライト脇のアオリ受けゴムが、年式によってデザインが違います。TNアクティと現行HA6/7後期型が一般的な丸型、HA6/7初期型が写真のようなウインカーに続く大型ゴム、HA1~4型は下の角を保護する形の角型です。 HA型からは右側のロープフックが牽引フック兼用のD型です。 テールゲートのロープフックはHA6/7初期型のみ2個、それ以外のHA型は3個あります。 ホンダコレクションホールにT360、TNトラック、ステップバン、バモスの展示があります。 添野清「ホンダの広告写真35年」にTNアクティまでのカタログがあります。 |
